|
*それぞれの質問をクリックしてください。回答へジャンプします。上から順番に見ていくこともできます。 ●Question9:あるお母様のお問い合わせメールに対する返信 「夏期講習の6日間で簡単な読解の方法を学ぶことができますか?」
●Question1:読書をすれば読解力がつくのですか? ●Question2:新聞を読めば読解力がつくのですか? ●Answer ただ本や新聞を読んでも効果はありません。書いてある内容がすぐには飲み込めないレベルの文章を選び、その内容を隅から隅まで把握できるまで徹底的に読み込まなければなりません。そのような方法・態度での読書をすれば読解力がつきます。 まず、読解力とは言語を道具とする思考力です。思考力とは論理力です。論理とは判断と推理のことですが、判断と推理を積み重ねて、「あることについてつじつまの合う理解や説明ができる」ということが、論理力であり思考力です。したがって、読解力とは、ある文章の内容についてつじつまの合う理解や説明ができるということです。
ここでおもしろいことに気づいてください。思考作業は「試行錯誤」の作業であるのです。あれこれ試行錯誤を経て、つじつまの合う説明に到着する。したがって、思考力をつけるためには試行錯誤をしなければならないのです。
私は、入試問題で充分な点数が取れないレベルの皆さんが、読解力をつけるためには、いわゆる「読書」は効果が少ないか、まったくないか、あるいは、有害であるとさえ思っています。それよりもむしろ入試問題集を一冊買ってきて、その文章を徹底的に読み込むほうが効果的に読解力をつけることができると思います。読書はそうして読解力をつけた後にすればよいのであり、読解力がないのに、「本を読めばよい」などという無責任なアドヴァイスを信じて、結局、読解力をつけずに終わる、ということのないようにしてほしいと思います。 また、「天声人語」を読めば読解力がつく、というのも間違いです。読解の基礎力をつけるにはもっと構成の明確な、内容のはっきりした論説文を選んで、練習台にすべきです。「天声人語」は随筆的な性質を多分に持つ点と含蓄や示唆に富む点で、論理力の練習台としては不向きです。 私は、これらの作品を否定しているわけでも、読むなといっているわけでもありません。読解力を「つける」ための練習台としては適切ではないと言っているに過ぎません。 *ちょっと無駄話をしますが、次の二つの英文の違いは分かりますか?
Who do you think is fit for the post, he or she?
Which is fit for the post, he or she?
“think”という動詞は、あれかこれかを選択するだけの場合には用いないからです。“think”という動詞は、「試行錯誤」の結果思考対象を明確化する場合に使うものであり、それぞれの人についてあれこれと適不適を考えることができ、どちらかを選択しなくてもよい場合に使うものだからです。故に、不特定範囲から対象を特定すべき“Who”とともに使われ、特定範囲の選択に過ぎない“Which”と一緒には使われないのです。つまり、英語でも“think”とは「試行錯誤」を本質とするものだということです。
●Question3:作文を書けば記述力がつくのですか? ●Answer ただ作文を書いても記述力はつきません。論理的に説明する作文の練習をしなければ記述力はつきません。 作文には、大別して二つがあると思ってください。一つは、「いつ・どこで・何が・どうした」という事実を中心とする作文。もう一つは、ある問題について答えを導くことを目的とし、そのための論理過程を示す作文。前者はいわば散文的作文であり、後者はいわば説明文的作文です。 ① まず、論理的な文章の書き写しをするのがよいでしょう。 ③ 第三に、論理的な文章の論旨を踏まえ、自分で具体例をあげて、筆者の論理を展開してみるとよいでしょう。 ④ 第四に、論理的な文章の論拠を踏まえた上で、これに反対する論理を展開してみるとよいでしょう。
●Question4:テクニックが大切ですか? ●Answer これは、一定の実力を前提として初めて役に立つものです。逆に、テクニックなどは一定の実力がついてくれば、自然と身についてくるものともいえます。分かりやすい例を出せば、イチローのテクニックは小手先だけのテクニックであるのか、実力であるのか、ということです。後者であることに異論はないはずです。たいして実力もないのに小手先のテクニックだけを求めていれば、永遠に実力をつけずに終わってしまいます。 ●Question5:傾向と対策が大切ですか? ●Answer 確かに多くの学校で「漢字は5問、物語文1問、論説文1問、記述中心」というような出題傾向はありますから、それを知っておくことは、試験を受ける以上必要不可欠なことです。しかし、これは大雑把な地図をもつということに過ぎません。 ●Question6:試験慣れが大切ですか? ●Answer 試験慣れが必要でないとはいえません。試験時間と試験内容の分量から、その問題をどのくらいのペースで解けばよいのかの感覚をつける必要はあるからです。
●Answer 以上でお分かりいただけると思いますが、国語は論理ですから、論理力を鍛えれば力はつくはずです。もちろん、論理力に才能というものもあるかもしれませんから、個人差はあるでしょうが、受験をするというような人で、まったく論理力がないという人はほとんどいないと思います。問題は明日を信じて論理力をつける努力をするかどうかの問題でしょう。 例えば「もう伸びません」などと悲観的に考える方がかなりたくさんいらっしゃいます。
●Answer Question1~3に対するAnswerを参照していただきたいのですが、国語に関する限り、漢字以外の宿題は無意味です。宿題を出して中途半端な予習をさせるよりも、授業の場で考えさせ、授業の場で解説し教える方がはるかに能率がよいといえます。鈴木国語では、漢字以外の宿題は出しませんが、読解力・記述力はもちろん、文法・知識の力まですべて授業の場で力をつけさせてきたと自負しております。なお、漢字は一定量を宿題として出すわけですが、漢字というものは、毎日、歯磨きのように、繰り返し習慣的に勉強すべきものですから、その限度で宿題を出しても、それは当然やるべき目安に過ぎないわけで、本当は宿題とは言えないわけです。 ●Question9:あるお母様のお問い合わせに対する返信メール 「夏期講習の6日間で簡単な読解の方法を学ぶことができますか?」 ●Answer お問い合わせありがとうございます。 「夏期講習の6日間で簡単な読解の方法を学ぶことができますか?」という点を中心にお答えいたします。 6日間でも「読解の方法」を学ぶことはできます。 しかし、6日間では「読解の方法」を体得することは通常はできないと思います。 「読解の方法」というものは、マニュアル化すれば、非常に単純なものになると思いますが、しかし、それを頭に入れたところで、文章の読解には役に立たないのが普通です。なぜなら、読解力をつけるためには、具体的な文章の論理的な分析を積み重ねることで、そこから経験的・帰納的に「読解の方法」を自分の中に作っていくことが必要だからです。抽象的に整理された読解マニュアルを知り、そこから演繹的に読解ができると思うのは大きな間違いです。 これは、特に不思議なことではなく、ピアノを弾く技術を身につける場合に、ピアノの弾き方マニュアルを覚えたところで、ピアノは弾けないのと同じことです。具体的な曲の練習の積み重ねを通して、弾き方を身につけていくしかないのと同じことです。 ただ、この読解技術の習得過程を合理化することはできます。昔の徒弟制度のように「何も教えないで学べ」というような不合理な方法ではなく、生徒が、「読解とは文章をこのように読むことであり、こう考えれば意味やテーマが納得できるのだ」と実感できるようにプリントや講義内容を工夫し、無理なく導くことで、読解の方法を比較的短期間で体得させていくことはできるのです。 しかし、それにしても、6日というのは時間的に短すぎます。6日ではワインは作れません。私はボジョレヌーボーのどこが良いのかわかりません。あんな未熟ものはワインではありません。 しかし、入試を最終目標にすれば、目標校合格レベルまで改善できるかもしれませんし、場合によっては最も得意科目にできるかもしれません。この点は極めて重要です。なぜなら、今国語が不得意なままで中学入試を突破したとしても、その後国語が得意科目になる機会はおそらく得られないからです。今度は大学入試で右往左往するだけだからです。逆に、中学入試の段階で国語に自信が持てれば、大学入試の国語に対しても立ち向かうことができるはずだからです。 そういう意味では、9月からでもぜひお通いいただきたいと思います。 ただし、メールの文面を拝見すると、お母様の勉強に対する考え方を大胆に変えていただく必要はあるように思います。 お母さま方は、「塾の日程を考えるとなかなか都合がつかなくて…」ということをおっしゃいますが、その塾の日程に意味があれば、国語力はついているはずではないのですか。塾に通うのは義務ではありません。勉強は自分の利益のためにするものであり、塾のためにするものではありません。今通っている塾の意味のない部分は切り捨て、意味のある部分だけ利用するというように発想を転換する必要があります。 お母さま方は、「塾の日程があるし、宿題もあるので、家庭教師ならなんとかなるのでは…」という発想で、現状を変えないで、家庭教師を付加するということをします。しかし、国語のプロ(?)家庭教師など役に立たないのが通常ですし、そもそも、何かを付加すれば現状が変わるという発想が間違っているのです。現状を変えるには、現状自体を自分で変革しなければなりません。デブはデブの現状を自分で変えるべきで、あやしい痩せ薬なんか飲んだところで意味はないのと同じです。 せっかくご質問いただいたのに、勝手なことを申し上げて申し訳ありません。しかし、鈴木国語はこのような「変な」考え方の塾であるということです。私のような過激な考え方は、寄らば大樹の現在の日本では異端に過ぎないでしょうが、私はどんな世の中でも私自身でありたいので、以上のようにお答えすることになった次第です。長々とすみません。 ご参考になれば、幸いです。 鈴木国語研究所・鈴木洋純 ページ・トップへ HPトップ ●Question10:低学年から勉強すれば読解力や記述力がつきますか?
●Answer 当研究所が4年生以下のコース設けていない理由について説明することで、回答とさせていただきます。 ページトップへ HPトップ ●Question11:大手塾と鈴木国語に通うのは体力的にきついのですが…? ●Answer 私は、国語(多くの人がやり方がよくわからない)だけは塾に通い、あとは過去問やネットを参考に自力で勉強する方が効率が良いのではないかと思いますが、特に大手塾との併用を否定するものではありません。 大手塾と鈴木国語に通う場合に、鈴木国語に通いきれないと言ってやめる生徒がいますが、通いきる生徒もいます。 両者の違いは何なのか、ということを改めて考えてみました。 一般にはすぐに「体力の違いだ」というような答えが返ってくると思われます。 しかし、「貧血」あるいは「低血圧」を思わせるような、どうみても「体力のない」女の子でも、ちゃんと鈴木国語に通いきり、国語も最後に大きな伸びを見せて桜蔭に合格した例もあります。この例からすると、単なる「体力」では説明できないものがあるように思います。 そもそも「体力」自体よく考えてみると内容の不明確な言葉です。 たとえば、柔道やレスリングや陸上短距離や水泳の選手は、たくさん食べて筋力も強く「体力」があると言えるでしょうが、マラソンの選手は体がボロボロになる一歩手前くらいの肉体で42.195キロを完走します。マラソン選手は「体力」はないというべきかもしれませんが、他の体力競技の選手はマラソンではマラソン選手に勝てません。 「体力」という言葉は世の中でなんとなく使われている内容の曖昧な言葉ではないのかと思われます。ちょうど血液型で人の性格を判断するのに近いような言葉ではないかと思います。 私は、勉強への対応力は、勉強の基本技術の問題ではないかと思います。 たとえば、小さい時から漢字の練習をしてきて、その習慣がついており、漢字に慣れている生徒にとっては、漢字をマスターすることはたやすいことです。「憂鬱」の「鬱」のような字にしても、いくつかのパート(「木」「缶」「木」「冖」「※」(←これは代用)「⊔」「匕」「彡」)に分けて覚え、それを再構成することは容易であり、すぐに覚えられるわけです。 これに対して、漢字練習の習慣がついていない生徒にとっては、外国人が漢字を習うのに近いものがあり、意味不明の記号を組み合わせるように感じられるのではないかということです。 前者はストレスなく、漢字をどんどんマスターできますが、後者にとっては漢字をマスターするためには大変なストレスに打ち勝たなければなりません。 それはちょうど、譜面の通りにピアノを弾ける人と全くのド素人の違いにも似ています。後者は鍵盤を抑えるだけでもかなりのストレスを感じます。 そして、この漢字を練習することにストレスを感じず、漢字を難なく覚えられるという基本的な技術(能力)が勉強にとって決定的な意味を持つのではないかということです。 こういう生徒は、読解にもとにかく取り組むという態度を持っています。解説もよく聞いてメモを取るということが自然にできます。やり直しも、涼しい顔をして短時間で正確にやり直します。一言でいえば、作業をいとわない、と言えるでしょう。 漢字練習という単純作業(というほど単純かどうかはさておき)をこなすという基本的能力が、勉強の推進力につながり、勉強の推進力がその読解・記述・選択の勉強を通して高度な思考力のトレーニングをもしてしまう、ということになるのだと思います。 こういう生徒は、大手塾と鈴木国語に通っても特に問題はなくこなしてしまいます。6年秋からの過去問指導や祝日特訓も出てきますし、講習などにもそれなりに出席します。 ところが、この単純作業能力が不十分な生徒は、そういうことが大きな負担になります。そこで、鈴木国語をやめれば負担が軽くなるように思ってやめます。しかし、やめて大手一本にしても、この能力を鍛えるわけではないので、結局伸びないで百人なみの結果になってしまうわけです。 ちなみに、秋からの大手塾の志望校対策に参加しなければならないというのも、鈴木国語をやめる理由とされます。志望校対策が本当に対策となっていればよいのですが、国語の過去問をむやみやたらにやって答え合わせだけしても、何の対策にもならない、ということはやめる皆さんはほとんど考えていないように思います。 話をもとに戻しましょう。この単純作業能力は、特に小さいうち(小4くらいまで)に身につけるとよいと思うのです(その意味で公文が良い)が、小さいうちから大手塾に入り塾らしいことをするものですから、この能力をしっかりと身につけないまま小6になり、受験を迎えてしましまうということになります。 では、小6になれば身につけられないかというと、そんなことはないと思います。トレーニングをすれば、小さい子より早く身につけることができるかもしれません。しかし、トレーニングをしないのです。難しい問題に目を奪われて、あるいは、宿題に追われて、あるいは、志望校対策とやらに気を取られて、たった10分のトレーニングをしないのです。自分向けにカスタマイズした勉強をしないで、自分以外のものに合わせようとするから、たった10分のトレーニングができないのです。 この基礎トレーニングの不足という問題は、たとえば、塾のトップのクラスの生徒と準トップのクラスの生徒との間の間の差ともなって表れます。両クラスのメンバーの大半は(多少の入れ替えはあっても)どちらかに偏っているはずです。準トップクラスの生徒はトップのクラスの生徒にはなかなか勝てません。 準トップのクラスの生徒がトップのクラスの生徒に決定的に勝つには、同じことをしないで、一旦自分の勉強の範囲を制限して、自分の勉強の内容をより徹底的なものにすべきです。つまり、たとえば、a・b・c・d・eという五つの項目をやらなければならないと思わないで、あえてa・b・cに限って、その代わり、a・b・cについては誰もかなわないほどの正確さとスピードで処理できるように徹底的にトレーニングするのです。これを繰り返していくと、残したd・eも難なくできるようになります。徹底的トレーニングを通して不足していた基礎技術を高度化することになるからです。そして、それに支えられて応用発展力も磨かれるからです。 これは、底辺のクラスあるいは中位のクラスから這い上がろうとする生徒にとっても、もちろん、大切なことです。 しかし、多くの人は自分独自のものを恐れます。できる限り人に合わせようとします。自分の人生をどうするかは自分で決めるしかなく、それが自由であり個性であるのに、それを恐れ嫌います。 だから、自分を伸ばさないのですが、これは私にはどうすることもできません。 ●Question12: 過去問を解けば合格できますか? 「徹底性」ということ ●Answer 「一発勝負」という言葉がある。しかし、例えば3発の弾丸を与えられて、その3発で的への命中を競う勝負をするとしても、それは3発勝負ではなく、3発の一発ごとがそれぞれ(一発)勝負なのだ。したがって、勝負というものは、常にすべて一回一回が勝負なのであり、「一発勝負」という言い方は奇妙だともいえる。「切り札」は「最後の手段としての札」なのに「最後の切り札」というのがおかしいのと似ている。また、勝負が本質的に一回一回のものであるとすれば、「三発勝負」「五発勝負」という言葉も成り立たないであろう。 ところで、「自分は横綱だから勝つはずだ」とか「大関だから勝つはずだ」と考える人間がいるとすれば、その人間は勝負師失格であろう。真の勝負師にとっては、一回一回の勝負が「勝負」なのであって、自分の「地位」に甘んずることはないであろう。「地位」は自分の過去の成果ではあっても、現在当面する勝負の結果を保証することはない「一期一会」ということも、芸術の勝負師の神髄を述べたものであろう。 ところが、こと受験になると、偏差値70超であるから合格可能性80パーセントというように、現在の地位と見込みが示される。いや、この点は、他のスポーツなどでも同じで、東の大関A山と西の幕の内二枚目B海は、過去10回対戦して、A山が8勝2敗であるというように資料が提示される。しかし、受験の場合には、それが単なる資料ではなく、何か合格を保証するもののように(過大評価されて)受け取られているのはなぜだろうか? 確かに、このくらいの成績の人間は5人中4人はほぼ間違いなく受かる。しかし、5人に1人は落ちるということでもある。決して、合格を保証するものではない。だから、この5人に入っているからといって安心はできない。この5人の中で1人はコロナウイルスに感染すると言われたら、この5人はかなりビビるだろう。そこで、感染対策というウイルスとの勝負が必要となる。同様に、本番の試験で落ちないための勝負が必要になる。それは、過去からの慣性の法則の延長(それは一種のマンネリ化では?)ではなく、鯉の滝登りのような一種の「飛躍」を成すことであろう。慣性の法則に足を取られ飛躍できない人間が5人に1人になるのかもしれない。 トップと目される受験生の5人に1人が落ちるとすれば、180人募集のトップ校では、その20%である36人がトップと目されるものの下から飛び上がってきた人間であるのだ。場合によっては二次募集に匹敵するほどの結構な人数である。 そこで、下積みのものが下剋上を成し遂げるには、どうすればよいかだが、それは、勉強対象を減らすことだと言ったら、驚くだろうか。 話を単純化するために、トップの生徒AをA=6x+10、それより成績下位の生徒BをB=3x+5としよう。同じxということを勉強するのに、AはBの2倍のスピードで勉強することになる。しかも、出発点はA10で、Bは5だ。Bは今のままの勉強ではAに追い付けない。そこで、睡眠時間を削ってでも勉強量を増やし、Aに追い付こうとする。いわゆる「はちまき」「根性!」という昭和というより、明治時代からの伝統に依拠したやり方だ。しかし、睡眠時間を削れば、寝不足で頭が回らず、勉強の能率は下がるという悪循環に陥る。悪くすれば、病気になる。このやり方では、BはAに追い付くことはできない。Bのやり方は勉強を単なる「量」と考える暗記主義的なやり方だ。 勉強の「質」を高めるのだ。A・B・C・D・Eの5項目をマスターしなければならないように見える場合にも、あえて現在の自分が対応できるA・B・CやA・Bをマスターすることに専念するのだ。ただし、A・B・CやA・Bは徹底的にマスターしなければならない。徹底的にマスターするとは、自由自在・縦横無尽に利用できるような感覚になるということだ。こういう「穴のある」しかし、徹底的な勉強を積み重ねると、それらが相互に関連しあって、今までわからなかったことがいつの間にかわかるようになり、解けなかった問題も解けるようになる。いつの間にか穴も埋まるというものだ。 「バカの一つ覚え」という他人をさげすむ言葉がある。しかし、「バカの徹底的な一つ覚え」を積み重ねれば、「バカ」は、もはやバカではなくなる。「バカ」をさげすむ人間は、「バカ」との相対的優位関係を根拠に「バカ」を見下すのだが、“There are more things in heaven and earth.”であることを知らない。所詮「井の中の蛙……」に過ぎない。自分が「バカ」であることを自覚し、そこから出発する。いわば、”knowledge of ignorance(無知の知)”だ。こうして、ソクラテスに帰依すれば、前述の5人の1人にならずに済むかもしれない。 ちなみに、「徹底的に」という言葉は勉強の世界では「死語」化していないだろうか。多くの人間が、「情報」をたくさん得て、次の日には、それを忘れている。「情報」ばかり、タブレットにため込んで、それを身に着けるということをしない。情報機器がない時代にも、外国語を身に着け、高い教養や思考力を身に着けた人間はたくさんいる。その人たちは何をしたのか。読書百遍というように徹底的にマスターする努力をしたのだ。そういう「脳」作業が必要なのだ。それはまた自分の手を使って「書く」という「仕事」でもあったのではないか。情報機器は発達しても、人間の脳の構造は特に進歩はしていないと思われる。むしろ退化しているかもしれない。漢字が書けなくなるというように。 さらに、ちなみに、過去問指導というのがある。志望校の過去問を10年分を解いて、最後に去年の過去問をやってどのくらい力がついているのか見るというような授業のことだ。受験の時期になると「過去問対策」のお祭り騒ぎが始まる。しかし、「徹底性」ということを意識している人はほとんどいないのではないかと思われる。過去問は、徹底的に研究・マスターすれば、それだけでも合格できる(少なくとも合格に大きく近づく)と言える。しかし、「過去問を解いてみた」程度の関わり方にとどまり、徹底研究・徹底マスターを欠く関わり方では合格には結びつかない。時間の無駄にすぎない。 ページ・トップへ HPトップ 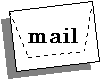 |